帰国予定の外国人であっても、社会保険への加入は原則として必要です
「日本で働くとき、社会保険には必ず入らないといけないの?」「自分は短期のつもりだけど、保険に加入する必要があるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
外国人労働者であっても、日本で就労する以上は日本人と同様に社会保険への加入義務が生じます。たとえ将来的に帰国を予定している場合であっても、労働条件が一定の基準を満たしていれば、原則として社会保険に加入する必要があります。
ここでいう「社会保険」とは、一般的に次の5つの保険制度を総称したものです。
- 健康保険
- 年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
ただし、実務の現場では「社会保険」という言葉が健康保険・年金保険・介護保険の3つを指して使われることも多く、意味の違いは文脈により判断する必要があります。
社会保険制度は、労働者本人の意思や国籍に関係なく、加入条件を満たした場合には「会社」と「従業員」の双方に加入義務が生じる制度です。
企業側が恣意的に加入を避けたり、「外国人だから」という理由で例外とすることはできません。
この加入義務に違反している場合、在留資格の審査に影響を及ぼす可能性があります。
そこでこの記事では、日本で働く外国人の方や、ビザ申請に向けて必要な知識を調べている方に向けて、外国人労働者にも適用される社会保険の種類や基本的な仕組み、申請時に気をつけたいポイントについて、やさしく解説しています。
なお、ビザ申請をご自身で行う場合には多くの情報を自分で調べる必要があります。「この内容で本当に大丈夫だろうか」といった不安がつきまとうことも少なくありません。また、入管への問い合わせは電話がつながりにくく、申請当日は長時間待たされることもあります。
調べものや手続きにかかる時間と労力を考えると、安心して進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効な選択肢の一つです。
当事務所では、ビザ申請に関するご相談から申請書類の作成・申請代行まで幅広くサポートしています。「申請ではどのような手続きが必要になるのか」と迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
「いきなり依頼するのは不安」という方のために、お試しとして初回無料相談をご用意しています。
無料相談では、状況を整理して許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントをご案内します。
▶ 初回無料相談のお申し込みはこちら
⚠️ 具体的な加入手続きや加入義務の判断については、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
1️⃣ 健康保険
健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう設けられた制度で、日本に住むすべての人が何らかの形で加入する必要があります。外国人の方も、在留資格により日本で就労する場合は、日本人と同様に健康保険への加入義務が発生します。
加入の対象者と事業所
- 法人(株式会社など)
→ 従業員が1人でもいれば健康保険への加入が義務づけられます(「適用事業所」)。 - 個人事業主(従業員5人以上)
→ サービス業・農林漁業等を除き、原則として健康保険への加入が必要です。 - それ以外の小規模事業所
→ 「任意適用事業所」となり、希望すれば加入可能です。
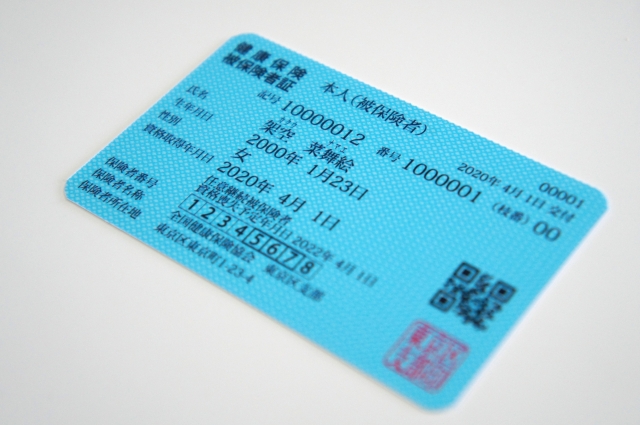
外国人労働者の取り扱い
外国人の方も、基本的には日本人と同じ扱いです。
- 医療費の自己負担は3割
- 配偶者や子が年収130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満であれば、被扶養者として保険に加入可能(扶養者本人が保険料を負担し、扶養者は支払不要)
加入手続きと注意点
- 就労により健康保険の対象となる場合、事業主が雇用から5日以内に「被保険者資格取得届」を年金事務所または事務センターに提出する必要があります。
- 健康保険に加入しない場合(たとえばアルバイトなどで条件を満たさない場合)でも、在留期間が3か月を超え、住民票がある外国人の方は、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険への加入が必要な場合
- 日本に上陸した日から14日以内に市区町村の窓口で手続きします。
- 届出が遅れた場合、加入日はさかのぼって適用され、その期間の保険料をまとめて支払う必要があるため注意が必要です。
2️⃣ 年金保険
日本の年金制度は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務がある「国民年金(基礎年金)」と、会社などに勤務している人が加入する「厚生年金」の2つから構成されています。
外国人であっても「日本に住んでいる」という点に着目されるため、日本国内で就労・居住している限り、日本人と同様に年金制度の対象となります。将来帰国する予定があるかどうかは、加入義務には関係ありません。
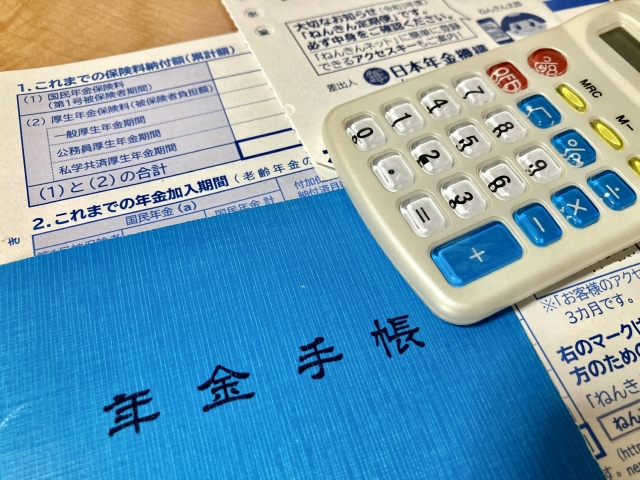
厚生年金の加入義務
- 法人(株式会社など)は厚生年金の適用事業所となり、従業員の加入が義務です。
- 個人事業主で常時5人以上の従業員を雇っている場合も、農林漁業やサービス業などを除き加入が必要です。
- 雇用されている外国人も、就労条件が満たされていれば厚生年金に加入します。
第3号被保険者の扱い(扶養家族)
- 配偶者が厚生年金に加入している場合、その扶養に入る配偶者や子どもは「第3号被保険者」として年金加入扱いとなり、保険料の負担なく将来年金を受け取る権利が得られます。
- 条件は年収が130万円未満かつ配偶者の年収の2分の1未満であることです。
国民年金の加入と注意点
厚生年金の適用がない場合(例えばアルバイトや短時間勤務など)でも、以下の条件を満たす外国人は国民年金に加入する必要があります。
- 在留期間が3か月を超える
- 住民票が作成されている
加入手続きは、日本に上陸した日から14日以内に市区町村役場で届出を行います。
期限後の届出も可能ですが、その場合は遡って保険料を支払う必要があり、未納が続くとビザ更新や永住申請に支障が出る場合もあります。
国民年金の未納と永住許可
- 国民年金を未納・滞納していた場合、原則として永住許可は下りません
- 特に、支払い遅れが1日でもあると不許可となる可能性が高く、非常に厳格に扱われます。
- 国民年金は納付書が届かないと支払いができないため、加入手続きは必ず期限内に行いましょう。
厚生年金と健康保険の一括手続き
会社での加入時には「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を作成し、年金事務所へ一括で提出します。
このため、以下のような組み合わせで加入することになります。
- 会社員の場合 → 厚生年金+健康保険
- フリーランスやアルバイト等 → 国民年金+国民健康保険
帰国する場合の年金はどうなる?
🔹 脱退一時金
外国人が日本を離れる際、「脱退一時金制度」を利用することで、支払った一部の年金を返金してもらうことが可能です。
- 対象者:日本国籍を持たず、年金の資格を喪失して出国した方
- 請求期限:日本に住所を有しなくなった日から2年以内
- 注意点:返金されるのは一部であり、受け取った場合には年金加入期間はリセットされます。
🔹 社会保障協定の活用
日本と協定を結んでいる一部の国では、「社会保障協定」によって以下が可能です。
- 両国の年金加入期間を通算して受給資格を満たす
- 支給される年金額は、実際の加入期間に応じた額のみ
協定国に該当する方は、この制度を活用することで将来的に年金受給の権利を維持できる可能性があります。
ー注意 ー
AIやGoogle検索、自動翻訳を含むネット上の情報は、古い内容や不正確な記載、表現の違いによって誤解が生じる場合があります。
必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切です。
「これで本当に大丈夫かな…」「何か抜けているかもしれない…」そんな不安を感じたときが、専門家に相談すべきタイミングです。
書類の整合性チェックから理由書の作成まで、すべて専門家がサポート。申請前に不安な点を整理しておくことで不許可のリスクを減らし、スムーズに審査へ進む準備ができます。
まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。
📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。
フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (1往復程度)も可能です。
「これで本当に大丈夫かな…」「何か抜けているかもしれない…」そんな不安を感じたときが、専門家に相談すべきタイミングです。
書類の整合性チェックから理由書の作成まで、すべて専門家がサポート。申請前に不安な点を整理しておくことで不許可のリスクを減らし、スムーズに審査へ進む準備ができます。まずは無料相談でご不安な点や現在の状況を整理してみてください。
📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
ご希望があれば、雇用理由書の作成から申請手続きまで一貫してサポートします。
フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (1往復程度)も可能です。
3️⃣ 介護保険
介護保険制度は、介護が必要になったときに社会全体で支え合うことを目的に設けられた公的保険制度です。外国人であっても、条件を満たせば日本人と同様に加入が義務付けられます。
対象者とサービス内容
介護保険のサービスを利用できるのは、以下の2つの条件のいずれかに該当する方です。
- 65歳以上で要介護状態にある方(第1号被保険者)
- 40~64歳で、特定の疾病により要支援・要介護状態となった方(第2号被保険者)
対象となる方は、訪問介護やデイサービス、訪問看護、施設入所などのサービスを、費用の一部自己負担で受けることができます。
保険料の支払い開始と納め方
介護保険料の納付は40歳の誕生日の月から開始されます。
- 会社の健康保険に加入している場合
→ 介護保険料は健康保険料に上乗せされて給与から天引きされます。
→ 保険料は都道府県ごとの保険料率で決まり、会社と本人で折半負担します。
→ 配偶者など扶養されている方は支払い不要です。
- 国民健康保険に加入している場合
→ 保険料は住んでいる自治体が決定し、以下の要素を組み合わせて計算されます。- 所得割(前年の所得に応じた割合)
- 均等割(世帯人数に応じた額)
- 平等割(一世帯ごとの定額)
- 資産割(固定資産等に応じた額)
→ 保険料率や算出方法は市区町村ごとに異なります
65歳以上の納付方法
65歳以上になると、介護保険料は原則として公的年金からの天引き(特別徴収)となり、市区町村が徴収を行います。
自己負担割合と給付限度額
介護サービスを利用した際の自己負担額は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかになります。
また、介護保険では以下のように「介護度」によって給付の上限額(=月額で使える保険内サービス費用)が設定されています。
- 要支援1・2
- 要介護1~5
介護度が重いほど支給限度額も高くなり、より多くのサービスを受けられる仕組みになっています。
4️⃣ 雇用保険と労災保険
「雇用保険」と「労災保険」は、あわせて「労働保険」と呼ばれます。どちらも外国人労働者を含め、労働者を雇用するすべての事業主に対して適用される重要な制度です。
雇用保険とは?
雇用保険は、失業・休業時の生活安定や再就職支援を目的とした保険制度です。主な給付には「失業給付」「育児休業給付」「介護休業給付」などがあり、働けなくなったときの生活保障に役立ちます。
労災保険とは?
労災保険は、業務中や通勤途中に発生したけがや病気、死亡事故などに対する補償制度です。治療費や休業補償、遺族給付などが支給されます。
加入の原則と対象者
労働保険は、事業の規模や業種を問わず、1人でも労働者を雇用していれば原則として適用が義務となります。
- 正社員・パート・アルバイトなど雇用形態は問わず
- 外国人労働者も日本人と同様に対象
- 保険料は原則として事業主が負担(雇用保険は労使折半)
雇用保険の適用除外となるケース
以下に該当する従業員は、雇用保険の対象外となります。
ただし、労災保険は例外なく適用されます。
- 契約期間が31日未満
- 所定労働時間が週20時間未満
- 昼間の学生(定時制・通信制・夜間部は除く)
外国人を雇用する際の届け出義務
外国人労働者を雇用した場合、事業主は「外国人雇用状況の届出」をハローワークへ提出する義務があります。
ただし、雇用保険に加入させる場合は、この届出を兼ねることが可能です(別途提出は不要)。
🔗関連記事:外国人の方を雇用した会社の届け出義務
最後に――ビザ申請をスムーズに進めたい方へ
ビザ申請では審査基準が頻繁に変更されるため、常に最新の情報に基づいて準備することが重要になります。しかし、インターネット上の情報は必ずしも最新とは限らず、AIによる判断が正確でないケースも少なくありません。
✅ 申請書類の準備方法がわからない
✅ 審査官が求めるポイントを押さえたい
✅ 不許可リスクを最小限に抑えたい
このようなお悩みをお持ちの方は、下記のリンクから無料相談をご利用ください。
現在の状況を確認し、個別の事情に応じて許可の見通しや申請時に押さえるべきポイントなどを丁寧にご案内します。
ご相談後、そのまま申請代行などをご依頼いただくことも可能です。
不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。
迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談 (メール1回分)が可能です。
ビザ申請の基礎知識や手続きに関する記事のピックアップ
ビザ申請に関する手続き(1)在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書(COE)は、外国人を日本に呼び寄せる際に必要なビザ申請の第一歩です。この記事では、交付申請の手続き対象者と申請場所、標準処理期間などをわかりやすく解説しています。
定住者ビザとは?対象者・申請条件・永住ビザとの違いをわかりやすく解説
定住者ビザは、一定の理由により日本での長期滞在が認められる在留資格です。この記事では、定住者ビザの取得条件や対象者、永住ビザとの違い、注意点などをビザ申請の専門家が丁寧に解説します。
2025年10月以降の外国免許切替の手続きと注意点|ビザとの関係も解説
外国の運転免許を日本で使うには「外免切替」の手続きが必要です。この記事では、免許切替の流れや必要書類、ビザ(在留資格)との関係をわかりやすく解説。当事務所は相談から申請手続きの代行まで幅広く対応しています。日本での生活・就労をスムーズに始めたい方はぜひご覧ください。







