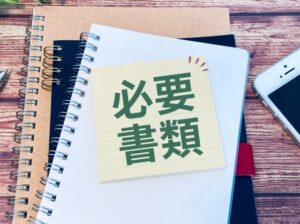帰化申請の審査は何を見られる?重視されるポイントと近年の傾向をわかりやすく解説


🔹 このページには帰化申請の審査傾向を箇条書きにして記載しています。
・帰化後に設定する本籍地は、自分で自由に決めることができます。ただし、これは現在の住所とは異なるものであるため、混同しないよう注意が必要です。
本籍とは、戸籍を置く場所のことであり、日本国籍を取得した後は、戸籍が新たに作成され、その際に本籍地も設定することになります。
本籍地として指定できるのは、日本国内の実在する地番(住所)に限られます。実際に居住していない場所でも、本籍として設定することは可能です。しかし、記載の際には正確な表記が必要です。地域によって地名の表記方法や地番の扱いに違いがある場合もあるため、必ず事前に本籍地として希望する市区町村の役所に問い合わせて、正式な記載方法を確認するようにしましょう。誤った表記で申請してしまうと、訂正手続きが必要になったり、手続きが遅れる原因にもなります。
・帰化後の氏名(姓および名前)は、原則として本人の希望に基づいて自由に決めることができます。
帰化によって日本国籍を取得する際には、日本の戸籍に新しく記載される氏名を自分で選ぶことができ、従来の母国で使っていた氏名をそのまま使用することも、新たに全く別の氏名に変更することも可能です。
ただし、自由に決められるとはいえ、いくつかの条件や制限も存在します。まず、氏名として使用できる漢字には制限があり、「常用漢字」と「人名用漢字」に限られています。読み仮名は自由ですが、あまりにも常識から逸脱した名前や、第三者に不快感を与えるような名前などは認められない可能性があります。
また、帰化申請書類には新しい氏名を記載する欄があり、その氏名が審査の対象となるため、法務局の担当官からその妥当性について質問されることもあります。たとえば、「姓と名のバランスが不自然ではないか」「不適切な漢字を使っていないか」「発音が極端に読みにくくないか」といった点が確認される場合があります。さらに、未成年の子どもがいる場合は、親と同じ氏にする必要があります。
帰化後の生活を見据えて、本人が長期的に使いやすい名前であること、周囲と問題なくやり取りできる名前であることが望ましいとされているため、申請前にしっかりと検討し、必要であれば法務局に事前相談するのが安心です。
・納税義務を履行し、過去5年間での交通違反が少ないこと、国民年金を支払っている事が必要です。
帰化申請を行う際には、日本での生活状況が適切であることを示すために、いくつかの重要な要件を満たしている必要があります。その一つが納税義務の履行です。所得税や住民税といった税金を期限内にきちんと納付していることが求められます。未納や滞納がある場合は、理由の如何を問わずマイナス評価となり、場合によっては申請が不許可になる可能性もあります。
加えて、交通違反歴も審査の対象となります。過去5年間の違反歴が重視され、特に軽微な違反であっても5回以内におさまっていることが一つの目安とされています。これを超える場合でも、必ずしも即不許可になるわけではありませんが、審査がより厳しくなり、追加の説明や反省文の提出を求められることがあります。飲酒運転や無免許運転などの重大な違反が含まれている場合は、より慎重な審査となる可能性が高まります。
また、国民年金の支払い状況についても確認されます。永住許可の申請では審査対象期間すべての月について納付実績が求められますが、帰化申請の場合は、原則として直近1から2年間分の納付があれば足りるとされています。とはいえ、年金の納付状況は社会的信用や義務を果たしているかの判断材料になるため、可能な限り継続的に支払っていることが望ましいといえるでしょう。
これらの要件を満たしているかどうかは、審査の重要な判断材料となるため、帰化申請前にあらためて確認し、不備がある場合はできる限り早めに是正することが大切です。
・自分と一緒に住んでいる家族の収入で生活するのに十分な金銭があることが求められます。
帰化申請においては、申請者が日本で安定した生活を継続できるかどうかが非常に重要な審査ポイントとなります。そのため、自身や同居する家族に安定した収入があり、経済的に自立していることが求められます。ここでいう「経済的自立」とは、国の支援や援助に頼らず、生活に必要な費用を自分たちの収入でまかなえる状態を指します。
このとき、銀行口座の預金残高が多いかどうかはそれほど重要視されません。もちろん全く貯金がないよりはあった方が望ましいのですが、最も重視されるのは「安定的な月収があるかどうか」です。審査では、基本的に月収が18万円以上であるかどうかが一つの基準とされており、継続的にこの水準の収入が得られているかを確認されます。
雇用形態については、正社員であることが理想ではありますが、契約社員や派遣社員であっても収入が安定していれば問題ありません。ただし、無職の場合は帰化申請を行っても認められることは非常に困難です。申請前に就職していることが前提になります。
なお、生活基盤としての住居については、持ち家か賃貸かは特に問われません。家の所有状況よりも、生活費を安定して支払い続けられる経済力があるかどうかが重要視されます。つまり、どのような形であれ、日常の生活を支えるに足る収入と継続的な就労状況が確認できれば、帰化申請において十分な条件を満たしていると判断されやすくなります。
・日本に帰化した場合に今の国籍を失うことができる必要があります。
日本に帰化するためには、現在の国籍を原則として離脱できること、つまり「元の国籍を失うことが可能である」ことが条件となります。これは、日本が二重国籍を基本的に認めていないためです。日本国籍を取得する際には、他の国の国籍を放棄する意思とその実行可能性が求められます。
ただし、国によっては法律上、自国民の国籍離脱に制限を設けている場合があります。特に注意が必要なのが「兵役義務」がある国です。例えば、台湾では兵役を終えていないと国籍を離脱することができず、結果として日本への帰化も認められない可能性があります。一方、韓国では兵役を終えていなくても国籍を離脱することができるため、日本への帰化が可能となる場合があります。
このように、帰化申請には「現在の国籍を放棄できるかどうか」という点が非常に重要です。国によって事情が異なるため、自国の国籍離脱条件について事前に確認しておくことが大切です。また、帰化の審査過程では日本の法務局からその可否や見込みについて説明を求められることもあるため、必要に応じて大使館や専門家に相談することをおすすめします。
・帰化申請をする際には、一定の日本語能力が求められます。
具体的には、日常生活に支障のない程度に日本語での会話ができ、基本的な読み書きができることが条件です。これは、申請者が今後日本で安定した生活を営むために必要不可欠な能力とされています。
一般的に要求される日本語レベルは「小学校3年生程度」と言われており、高度な文法や語彙は必要ありません。実際には、法務局で簡単な日本語テストが行われることがあります。このテストでは、たとえば「ひらがなで書かれた文章の中からカタカナに直すべき言葉を見つけてカタカナに書き直す」といった内容が出題されます。他にも簡単な文章の読解や、住所や名前の記入といった実生活に即した問題が出ることがあります。
このように、特別な勉強をしなくても、普段から日本で生活していれば十分に対応できる内容です。ただし、まったく日本語が読めない・書けないという場合には、帰化が難しくなることもありますので、不安な場合は事前に日本語学習を進めておくと安心です。
・記入項目がないのであれば空欄にはせず、「なし」とはっきり記入する必要があります。
帰化申請書類を作成する際、記入項目があっても自分に該当しない内容である場合には、空欄のままにしてはいけません。記入すべき内容が「ない」場合でも、必ず「なし」または「該当なし」などの記載を明確に記入する必要があります。
これは、申請書類を審査する法務局の担当者が「この項目を見落として空欄にしているのか」「意図的に記入していないのか」を判断できなくなるのを防ぐためです。たとえ申請者にとっては「書くことがないのは当然」と思える項目であっても、審査を受ける以上、形式的な記載ルールを守ることが重要です。
特に、親族関係や職歴、婚姻歴、資産の有無などの欄は、たとえ該当がなくても必ず「なし」と記載してください。空欄のままだと「未記入」として不備扱いになり、差し戻されたり、追加の確認が必要になったりして審査に余計な時間がかかってしまうおそれがあります。
帰化申請は書類の量が多く、記載漏れや形式の不備があると全体の審査が大きく遅れてしまいます。申請書類を提出する際は、「自分が書くべき項目がない=『なし』と記載する」が基本であると理解し、すべての項目を埋める意識で丁寧に作成しましょう。
・申請書類のうち、法務局の国籍課で配布される「帰化申請書」は、原則として相談時に1人1部しか交付されません。
つまり、記入を間違えたり、清書時に書き損じた場合でも、すぐに新しい用紙をもらえるとは限らないため、注意が必要です。
そのため、当事務所ではあらかじめWordやExcelなどのソフトを使用して、申請書・履歴書などの様式をパソコン上で作成しています。これにより、記載内容の修正やレイアウト調整が簡単にでき、正確かつ見やすい書類を効率よく仕上げることが可能になります。
特に帰化申請では、記載ミスや記入漏れがあると法務局での再提出を求められることもあるため、作成段階での丁寧な準備が非常に重要です。書き間違いによる手戻りや、再発行の手間を省くためにも、最初からデジタルデータで申請書を整える方法が非常に有効です。
・出入国歴は通常パス-ポ-トで確認します。件数が多い方の場合には法務省から出入国歴をもらいチェックする必要があります。
出入国の履歴は、通常はご本人のパスポートに押された出入国スタンプを確認することで把握します。ただし、出入国の回数が非常に多く、スタンプが複数のパスポートにまたがっていたり、押印が不鮮明で読み取れない場合などは、パスポートだけで正確な履歴を確認することが難しくなります。
そのような場合には、法務省(入国管理局)から「出入国記録(出入国履歴)」を取得して確認することが推奨されます。この記録は、申請者本人が請求することによって発行してもらえるもので、帰化申請において非常に重要な参考資料になります。
また、帰化申請では「継続して日本に居住していること」が重要な要件とされており、特に注意すべきなのが1回の出国期間です。1回の出国が90日(約3か月)を超えてしまうと、それまでに積み重ねてきた日本での居住期間がリセットされる可能性があります。これは、たとえそれ以前に何年も日本に住んでいたとしても、90日を超える長期の出国があると「継続居住」とはみなされなくなるということです。
したがって、過去の出入国履歴の正確な把握と、長期出国がないかの確認は、帰化申請の準備において非常に重要なポイントとなります。
・帰化申請における「動機書」は、申請者本人が手書きで作成することが求められます。用紙のサイズはA4で1枚程度が目安です。
内容については、必ずしも難しい文章や立派な理由を書く必要はなく、あくまで「本人の言葉で書かれた誠実な内容」であることが大切です。
記載内容としては、まず簡単な自己紹介(氏名、出身国、来日時期など)から始め、自分の経歴や現在の生活状況について簡潔に触れたうえで、なぜ日本への帰化を希望するのかという「動機」を自分の言葉で書きましょう。たとえば「長く日本で暮らしており、これからも日本で生活していくため」や「子どもが日本で育っており、日本社会の一員として責任を果たしたい」など、ごく自然な理由で構いません。
東京出入国在留管理局での在留資格申請と異なり、この動機書の内容が「立派であるか」「文章が上手であるか」といったことが審査結果に大きく影響するわけではありません。むしろ、本人の素直な気持ちが伝わることが重視されます。そのため、難しく考えすぎず、ご自身の思いを丁寧に手書きでまとめることが大切です。
「調べるのが大変…」「書類作成は不安…」そんなときは専門家にお任せください。
複雑な調査や書類作成はすべてプロが対応しますので、あなたは最小限の準備だけで済みます。まずはお気軽にご相談いただき、申請をラクに進めましょう。
💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
※個別事情に合わせて、許可の可能性と今後の手続きの流れについて丁寧にご案内します。ご相談後、そのまま書類作成代行をご依頼いただくことも可能です。
「調べるのが大変…」「書類作成は不安…」そんなときは専門家にお任せください。
複雑な調査や書類作成はすべてプロが対応しますので、あなたは最小限の準備だけで済みます。まずはお気軽にご相談いただき、申請をラクに進めましょう。
💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
※個別事情に合わせて、許可の可能性と今後の手続きの流れについて丁寧にご案内します。ご相談後、そのまま書類作成代行をご依頼いただくことも可能です。
・コピ-の方法も、真ん中央の位置でコピ-すると決められています。
コピーの方法にも一定のルールがあります。法務局で提出する書類については、用紙の中央に原本を正確に配置してコピーをとることが求められています。これは、提出書類の形式や整合性を重視する法務局の運用方針に基づくものです。
一方で、東京出入国在留管理局に提出する場合には、こうしたコピー位置に関する明確な指定はありません。多少ずれていても問題になることは少なく、形式よりも内容が重視される傾向にあります。
ただし、いずれの機関でも、コピーの品質が不鮮明だったり、一部が切れていたりするような場合は再提出を求められることがあります。提出前には、コピー内容がはっきり読み取れるか、余白や配置が不自然でないかを必ず確認しましょう。
・源泉徴収票は、帰化申請において非常に重要な書類の一つです。
ここでは主に年収の金額や、扶養している家族の有無などがチェックされます。
特に注意が必要なのは、本国に住む家族を扶養親族として申告している場合です。このような場合には、実際にその家族に対して定期的に送金しているかどうかを確認されます。なぜなら、送金していないにもかかわらず扶養控除を受けていた場合には、所得税の不正申告=脱税と見なされる可能性があるからです。
そのため、家族を扶養親族として申告している方は、送金の事実を証明できる書類(例:海外送金の控えや明細など)をしっかり準備することが必要です。送金額や頻度について明確な基準があるわけではありませんが、扶養とみなされるに足る実態が求められます。
帰化申請では、税金の適正な納付状況も重要な審査項目の一つです。申告内容と実態が一致していることを裏付ける書類を用意しておくことで、スムーズな審査につながります。
・帰化申請では自宅付近や勤務先付近の地図を提出します。
提出する地図については、Googleマップで自宅から勤務先や通学先までの経路を指定し、その画面をスクリーンショットしたものを使用して問題ありません。特別な形式や書式は求められておらず、画面上にルートや所要時間、出発地と目的地がきちんと表示されていれば十分です。
スクリーンショットを提出する際は、なるべく地図全体が見えるようにし、必要に応じて拡大・縮小して見やすく調整しましょう。また、画面上に日時や交通手段(徒歩・電車・バスなど)も表示されていると、より正確に状況を伝えることができます。
なお、Googleマップのスクリーンショットを提出書類として利用する場合、私的使用または非公開での利用にあたる限り、著作権上の問題は基本的に生じません。つまり、以下のような条件を満たしていれば問題ないと考えられます。
🔹 著作権上問題がない利用の条件
- Googleマップの著作権表示(© Google など)を削除しない
- 行政機関への申請など、公的な提出書類としての使用
- インターネット上に公開しない
- 営利目的で使用しない
・帰化申請の手続きにおいては、法務局によって運用方針や対応が異なる場合があります。
たとえば、提出する書類がすべて完璧にそろっており、形式上も内容上も不備がない場合でも、初回の相談時に申請を受理してくれる法務局もあれば、そうでないところもあります。
たとえば、埼玉県内の法務局では初回の相談で申請書類が完璧に整っていたとしても、原則として申請を受け付けない運用となっています。初回相談はあくまで事前確認の位置づけであり、必要な書類の確認や説明が中心です。実際に申請書を提出できるのは2回目以降の相談時とされています。
このように、各地の法務局では申請の受付基準や手続きの流れに違いがあるため、事前に該当する法務局へ確認のうえ、スケジュールや準備内容を調整することが重要です。特に相談予約の時点で「初回に提出は可能かどうか」を確認しておくことで、余計な手間や時間を省くことができます。
最後に――帰化申請の審査で不安を感じていませんか?
帰化申請は、提出書類の内容や説明の仕方によって結果が大きく左右されます。また、近年は審査の傾向も変化しており、過去の情報やAIでは対応しきれないケースも増えています。
✅ 最近の審査ポイントを知りたい
✅ どんな書類が必要なのか整理したい
✅ 不許可を避けてスムーズに進めたい
このような不安を感じている方は、ぜひお問い合わせ(初回相談無料)をご利用ください。個別事情に合わせて、許可の可能性と今後の手続きの流れについて丁寧にご案内します。
ご相談後、そのまま申請書類の作成代行をご依頼いただくことも可能です。ご依頼いただければ、専門家があなたの状況に合わせて、必要書類の準備から面接での対応まで丁寧にサポートいたします。不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心してお仕事や日常生活に専念していただけます。
迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
※ フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談(メール1回分)が可能です。
帰化申請に関する当事務所のサービス

事務所案内
当事務所の理念や対応可能な相談内容、所在地、アクセスなどご案内します。

サービス紹介
帰化申請を専門家が丁寧にサポートします。お気軽にご連絡ください。

依頼の流れと料金案内
帰化申請サポートの依頼の流れと料金をご案内します。
帰化申請に関する記事のピックアップ
帰化申請の手続きの流れとかかる時間は?
日本での生活が長く、帰化を検討している外国人の方へ。帰化申請にかかる期間の目安や申請の流れを分かりやすく解説し、トラブルを避けるためのポイントもご紹介します。日本国籍の取得を目指す方は、ぜひご相談ください。書類作成の代行にも対応しております。
帰化後に必要な手続きガイド|住民登録やパスポート取得を徹底解説
帰化後に必要な手続きや注意点を解説!住民票の変更やパスポート取得、国籍離脱手続きなど、スムーズに進めるための情報をお届けします。帰化手続きでお困りなら神山行政書士事務所にご相談ください!
帰化申請の必要書類|作成が必要な書類の書き方と注意点
帰化申請では、多くの書類を準備する必要があります。本ページではその中でも特に「作成が必要な書類」に焦点を当て、書き方や注意点をわかりやすく解説します。自分で進めるのが不安な方は、ぜひ専門家にご相談ください。初回相談は無料で承っています。
帰化申請の必要書類|公的機関から取得する書類と注意点
帰化申請によって日本国籍を取得するには、多くの提出書類が必要です。本記事では、その中でも公的機関から取得する書類と注意点について解説します。帰化申請を検討中で、書類準備にお困りの外国人の方は、ぜひご相談ください。