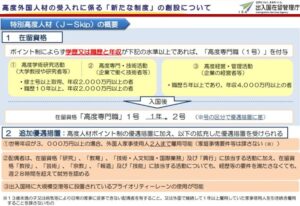2027年から始まる「育成就労制度」と「技能実習制度」の違いを解説
技能実習制度は、開発途上国などの外国人を受け入れ、日本で技術や知識を学ばせ、それを母国に還元することで経済発展を促進することを目的としていました。
しかし、実際には低賃金労働や長時間労働などの問題が多発し、言語の壁も改善を難しくする要因となっていました。

海外からの批判も高まる中、2024年3月に技能実習制度の廃止と「育成就労制度」への移行が閣議決定され、2027年頃の開始が予定されています。
そこで本ページでは、2024年11月現在で厚生労働省が公表している内容に基づき、育成就労制度の概要とその特徴を解説します。ただし、制度が開始されるまでに変更される可能性がある点をご承知ください。また、技能実習制度や育成就労制度の在留期間終了時には「終了」ではなく「修了」という表記を使用しています。なお、特定技能制度は適正化を図りつつ、現行制度を継続する予定です。
📌「技能実習」との主な違いは?
技能実習制度と育成就労制度の主な違いを次の表にまとめました。
| 技能実習制度 | 育成就労制度 | |
|---|---|---|
| 制度目的 | 国際貢献 | 人材育成、人材確保 |
| 修了後 | 帰国が前提 | 特定技能へ移行 |
| 在留期間 | 最長5年 | 原則3年 |
| 職種 | 91職種167作業 (令和6年9月30日時点) | 特定産業分野に限定される予定 |
| 転籍 | 原則不可 | 条件を満たせば可能 |
| 日本語能力 | 原則は規定なし ただし「介護」は日本語能力試験N4 | 日本語能力試験N5 又はそれに相当する日本語講習の受講 |
| 監理団体の名称 | 監理団体 | 管理支援団体 |
以下、それぞれについて見ていきます。
🔹 制度の目的と修了後の展望
技能実習制度は「開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力すること」、すなわち国際貢献を目的として設計されていました。このため、技能実習生が日本で学んだ技術や知識を母国へ持ち帰り、そこで活用することが重視されていました。そのため、技能実習制度では在留期間が修了した後、母国への帰国を前提としていました。
一方で、育成就労制度は、日本が「外国人から選ばれる国」となることを目指し、人材を確保することを主な目的としています。特に人手不足が顕著な分野で必要な人材を育成し、日本の産業を支える基盤を強化することに重点が置かれています。このため、育成就労制度では修了後に「特定技能1号」への移行を前提とし、引き続き日本での就労が可能な設計になっています。
育成就労制度は「特定技能」の前段階の在留資格として位置付けられ、外国人の方が日本でキャリアアップしながら長期的に貢献できる仕組みを整えています。
📌【育成就労制度及び特定技能制度の流れ】
育成就労(3年) → 特定技能1号(5年) → 特定技能2号(制限なし)
ビザを変更しつつキャリアアップを図り、長く日本に滞在してもらうことで人手不足分野における人材を確保する
📅 在留期間の比較
技能実習制度における在留期間
技能実習1号は、技能実習生が入国1年目に取得する在留資格であり、滞在可能な期間は1年間です。ただし、この1年間には、原則として最初の1~2ヶ月間の入国後講習が含まれています。そのため、実際に受入れ企業で実習を行える期間は、1年よりも短くなるのが一般的です。
1年間の滞在を超えて日本に滞在するためには、技能実習2号への在留資格変更が必要です。この2号では、最長2年間の滞在が可能となります(1年ごとに更新可能)。さらに滞在期間を延長する場合には、技能実習3号への移行が可能です。3号では、同様に1年ごとに更新でき、最長2年間の滞在が許可されます。
したがって、技能実習制度では1年(1号)+2年(2号)+2年(3号)で、最長5年間の滞在が可能となる仕組みになっています。
育成就労制度における在留期間
育成就労制度では、「原則3年」とされています。この原則3年が具体的にどのように運用されるかについては、現在詳細が明らかにされていませんが、以下の2つの運用形態が考えられます。
- 1年ごとの許可更新型
初回の在留期間として1年が許可され、その後2回まで更新が可能となり、最長3年間滞在できる形。 - 一括で3年間の許可型
初回申請時に一括で3年間の在留期間が許可される形。
どちらの形態になるかは未定ですが、いずれの場合も育成の進捗を確認するための「評価試験」や「報告義務」などの仕組みが導入される可能性があります。特に、一括3年の許可型の場合、途中で人材育成状況を測定する中間評価が課されることが予想されます。
📌 技能実習制度との違い
技能実習制度では、在留期間の延長を複数回申請しなければならないため、手続きの頻度が高くなりがちです。一方、育成就労制度では、最長3年の滞在が一貫して計画されており、滞在中の手続きが簡略化されることが期待されています。
育成就労制度は、技能実習制度とは異なり、修了後のキャリアパスが特定技能制度と密接に結び付いているため、滞在期間の運用方法にも柔軟性が持たされることが見込まれます。日本国内での長期的な人材確保と育成を目指す新たな仕組みとして、期待が寄せられています。
「調べるのが大変…」「書類作成は不安…」そんなときは専門家にお任せください。
複雑な調査や書類作成はすべてプロが対応しますので、あなたは最小限の準備だけで済みます。まずはお気軽にご相談いただき、申請をラクに進めましょう。
💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
※個別の事情に応じて、許可の可能性や申請手続きの流れを丁寧にご案内します。ご相談後、そのまま申請代行をご依頼いただくことも可能です。
「調べるのが大変…」「書類作成は不安…」そんなときは専門家にお任せください。
複雑な調査や書類作成はすべてプロが対応しますので、あなたは最小限の準備だけで済みます。まずはお気軽にご相談いただき、申請をラクに進めましょう。
💡 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
※個別の事情に応じて、許可の可能性や申請手続きの流れを丁寧にご案内します。ご相談後、そのまま申請代行をご依頼いただくことも可能です。
1️⃣ 職種と対象分野の変更点
✅ 技能実習制度の職種
技能実習制度では、令和6年9月30日時点で91職種167作業が対象とされており、これらの職種が細分化されているため、実際に行える業務の範囲が非常に限定的です。この細分化により、対応する「特定産業分野」を持たない職種も存在し、試験免除で特定技能に移行できない職種や作業が全体の約15%に及ぶという課題があります。
✅ 育成就労制度の職種
育成就労制度では、技能実習制度の職種をそのまま引き継ぐのではなく、対象となる業種を再設定し、特定技能制度における「特定産業分野」と一致させる形で整理される予定です。
特定技能制度は、2024年現在で12分野14業種が対象となっており、技能実習制度に比べて範囲が広く、業務内容にも柔軟性が持たされています。この統一により、育成就労制度から特定技能に移行する際、試験免除で移行できない分野が存在しないことが期待されています。
新制度の進捗と見通し
育成就労制度で対象とされる産業分野の具体的な設定については、2025年から2026年初めにかけて検討が行われる予定です。この見直しは、技能実習制度の課題を解消しつつ、日本国内の人材不足に対応する仕組みを構築することを目指しています。
2️⃣ 転籍の概要と新制度での改善点
転籍とは、現在の受入れ企業との労働契約を終了し、新しい企業と労働契約を結ぶことを指します。しかし、技能実習制度では「やむを得ない場合」を除いて転籍が認められていません。この「やむを得ない場合」と判断される具体例は以下の通りです。
📌【技能実習制度で転籍が「やむを得ない場合」とされる主なケース】
- 実習実施者の経営上・事業上の都合
- 実習認定の取消し
- 実習実施者における労使間の諸問題
- 実習実施者による暴行などの人権侵害行為、または対人関係の諸問題
ただし、「労使間の諸問題」や「対人関係の諸問題」に具体的にどのようなケースが該当するのかは明文化されておらず、これが原因で転籍が難しいという現状がありました。この背景には、技能実習生が“実習生”という立場にあるため、転籍の概念が制度設計と馴染まなかったことが影響していると考えられます。
民間職業紹介事業者の関与制限と新たな支援体制
育成就労制度では、これまで技能実習制度で曖昧だった「やむを得ない事情」による転籍の基準を明確化し、手続きの柔軟化を図る予定です。この改正により、転籍がよりスムーズに行えるようになります。
さらに、一定の条件を満たした場合には、本人の意向による転籍も認められる方針です。以下はその試案として挙げられている条件です。
📌【本人の意向による転籍(試案段階)】
- 一定期間以上の就労経験
同一の機関で1~2年程度の就労期間を満了していることが条件とされます。 - 技能検定試験または日本語能力試験の合格
技能検定基礎級などの技能試験や、N4~N3レベルの日本語能力試験に合格していることが求められます。 - 適切な転籍先
転籍先が法令や規定に適合し、受入れ条件を満たしていること。
これにより、外国人労働者のキャリアパスが柔軟化し、より良い環境での就労が可能となることが期待されています。
⚠️ 2024年11月1日改正の運用要領
育成就労制度の導入を見据え、2024年11月1日に技能実習制度の運用要領が改正されました。この改正では、以下のような改善点が盛り込まれています。
- 「やむを得ない事情」の具体化
転籍が認められる状況を明確化することで、適切な判断が可能に。 - 転籍手続きの簡素化と柔軟化
手続きの負担を軽減し、スムーズな転籍を支援。 - 生活支援の強化
在留管理制度に基づく生活支援措置を実施。
これらの改正により、外国人労働者がより適切な環境で働けるようになることが期待されています。
3️⃣ 日本語能力について
技能実習の場合、介護分野など一部の例外を除き、日本語能力に関する具体的な要件は法律上明記されていません。しかし、実際には技能実習生送り出し機関において、来日前に6ヶ月ほど日本語を学習するのが一般的です。ただし、送り出し機関での学習は日本人講師ではなく、母国の日本語講師が指導することが多いため、十分に流暢な日本語を話せるようになるケースは少ないのが現状です。そのため、初めて来日する技能実習生の多くは日本語能力試験(JLPT)のN5レベル(基本的な日本語がある程度理解できるレベル)程度の日本語力を有しています。
一方で、育成就労制度では、法律に基づいて日本語能力に関する要件が設定されています。具体的には、就労開始前に以下のいずれかを満たすことが求められます。
- 日本語能力試験(JLPT)のN5レベル以上に合格していること
- 認定日本語教育機関で一定の日本語講習を受講していること
これにより、育成就労制度では日本語能力を一定水準以上に維持し、労働環境での円滑なコミュニケーションを図ることが期待されています。
4️⃣ 監理団体の名称が変更に
技能実習制度の反省を踏まえ、育成就労制度では受入れ機関と密接な関係を持つ役職員の監理業務への関与が制限されるほか、外部監査人の設置が義務化される予定です。このような改革により、監理団体の独立性と中立性を担保し、特定技能外国人の支援業務は登録支援機関への委託に限定される方針となっています。これに伴い、現在の「監理団体」は、育成就労制度が実施されると「監理支援機関」へと名称が変更されます。
「監理支援機関」は、監理団体と同様に、主務大臣の許可を受けた上で次のような業務を行います。
- 国際的なマッチング:海外の送り出し機関との調整や人材の紹介
- 受入れ機関への監理・指導:育成就労実施者に対する適切な指導
- 育成就労外国人の支援と保護:生活や就労に関する包括的な支援
ただし、現在の監理団体が自動的に監理支援機関となるわけではありません。育成就労制度で監理支援機関として活動するためには、新たに監理支援機関としての許可を受ける必要があります。この許可は、独立性や透明性を確保するための重要な要件です。
2026年中ごろから、育成就労制度の開始に向けて許可申請の受付が開始される予定です。しかし、現時点(2024年11月)では具体的な申請開始日はまだ確定していません。監理団体が引き続き外国人の監理業務に関わるためには、許可要件を満たし、適時申請を行う必要があります。
💡 移行措置について
育成就労制度の開始は2027年を予定しています。この制度への移行にあたって、開始前から技能実習を行っている方々に対する移行措置が設けられる予定です。具体的には、開始日前に入国し、開始日時点で現に技能実習を行っている場合には、引き続き技能実習を継続することが認められます。
また、開始日前に技能実習計画(育成就労制度開始日から3か月以内に開始する内容を含む計画)の認定申請を行っている場合、開始日以後に技能実習生として入国することが可能とされています。この場合も、技能実習制度のルールが適用され、技能実習から育成就労への移行は認められない点には注意が必要です。
移行措置の内容は現時点(2024年11月)では一部に限られているため、引き続き公式発表や関係機関からの最新情報を確認する必要があります。
最後に――就労ビザの申請でお困りではありませんか?
就労ビザ申請では、正しい在留資格の選定と書類の準備、審査基準の理解が重要です。不備があると不許可の可能性もあります。
✅ どの就労ビザが適しているかわからない
✅ 必要な書類や審査のポイントを知りたい
✅ 不許可リスクを最小限に抑えたい
このようなお悩みがある企業さまは、お問い合わせ(初回相談無料)をご利用ください。個別の事情に応じて、許可の可能性や申請手続きの流れを丁寧にご案内します。
ご相談後、そのまま申請代行をご依頼いただくことも可能です。ご依頼いただければ、御社の状況にあわせて必要書類リストの提示から申請書・理由書の作成、入管とのやり取りまで一括してサポートいたします。不許可リスクを減らし、準備の負担を大幅に軽減できるため、安心して本業に専念していただけます。
迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
📍 初回相談無料(メール1–2往復/オンライン相談30分)|1–2営業日以内に返信
※ フォーム入力が面倒な方は、LINEでも簡単なご相談(メール1回分)が可能です。
就労ビザに関する当事務所のサービス

事務所案内
当事務所の理念や対応可能な相談内容、所在地、アクセスなどご案内します。

サービス紹介
就労ビザ申請は、ビザ申請の専門家が丸ごとサポートします。

依頼の流れと料金案内
就労ビザの申請代行について、依頼の流れと料金をご案内します。
就労ビザに関する記事のピックアップ
技術・人文知識・国際業務ビザの更新申請ガイド
外国人採用をご担当されている企業の皆さまへ。本記事では、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の更新手続きについて詳しく解説します。必要書類や提出先、審査で重視されるポイントを整理するとともに、不許可になりやすいケースとその対策もわかりやすく紹介します。
建設業・工事業の外国人雇用|必要な就労ビザと取得条件
建設・工事業で外国人を雇用予定の企業ご担当者さまへ。必要な就労ビザの種類や取得条件、メリットや注意点について、ビザ申請専門の行政書士がわかりやすく解説します。
技人国から永住ビザの取得方法と申請手続きガイド
技人国ビザから永住権取得を目指す方へ。申請に必要な条件や書類、審査で重視されるポイントをわかりやすく解説します。不許可を避けるためのチェックポイントも紹介します。